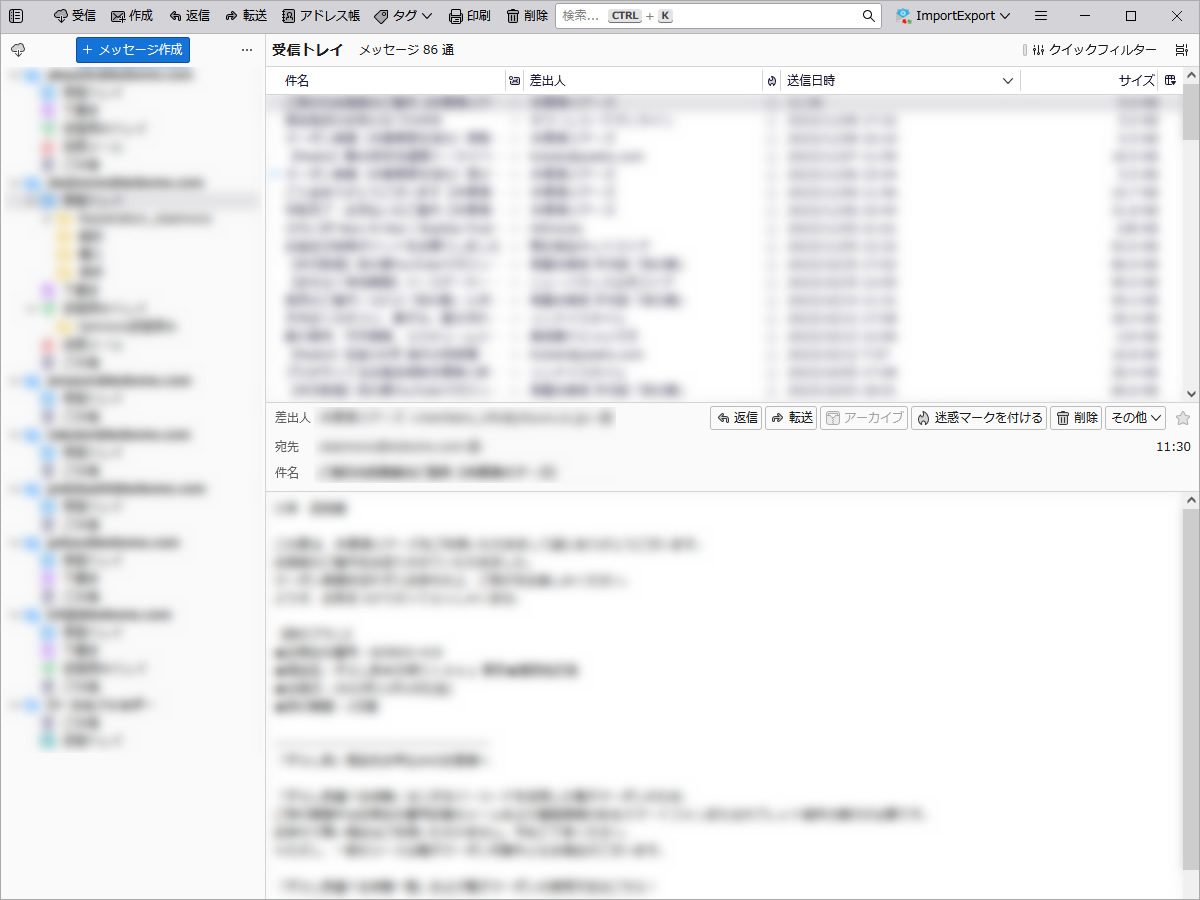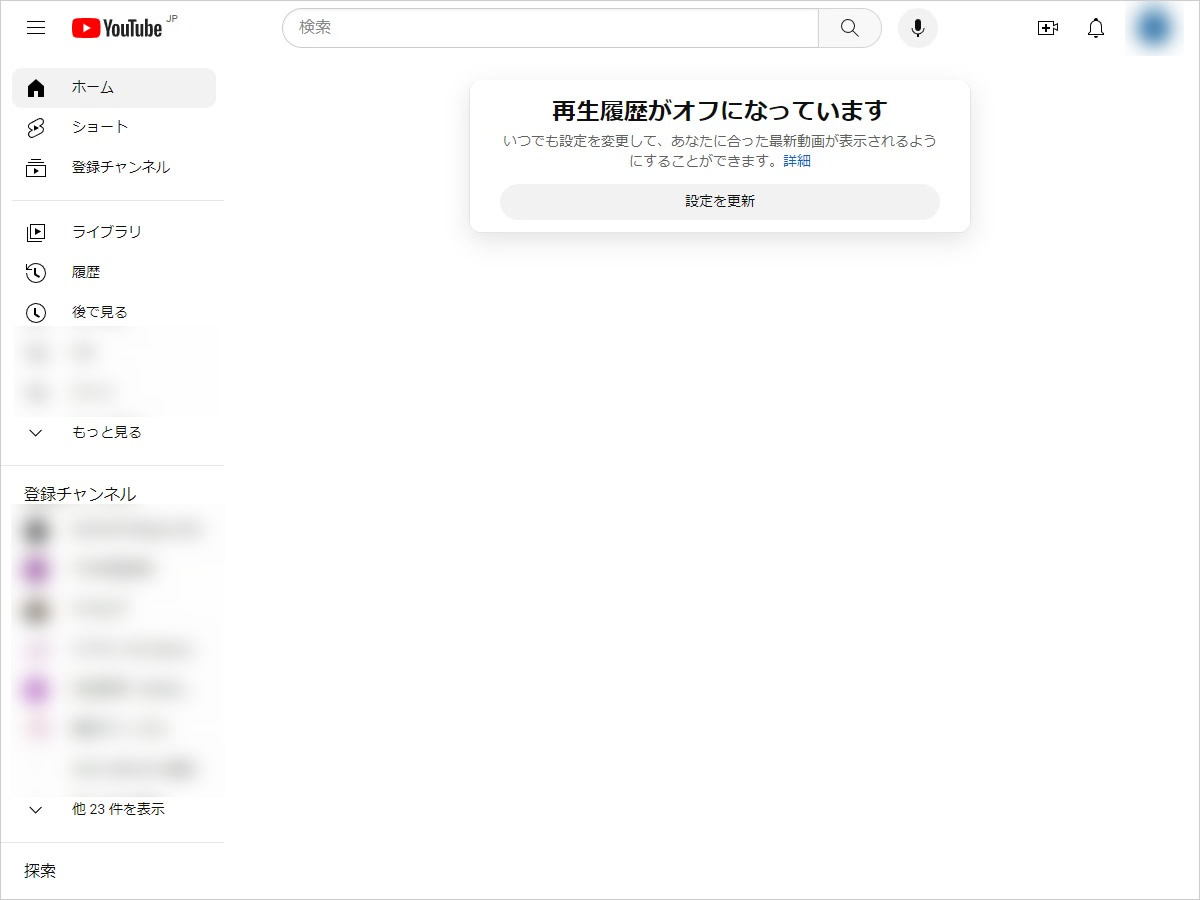旧『なにわの海の時空館』の利活用事業にかかる事業予定者が決定したそうだ。市のウェブページによれば、応募は2者あったが1者は辞退したので、残る1者が必然的に選ばれたようだ。
提案概要のPDFが用意されていたので拝見したが、目を引いたのはドーム内のイメージパース。ドームでは「ラグジュアリーサービス」が提供されるようで、菱垣廻船をステージに仕立てショーが催されている。でも客はステージには背を向けワイン片手に歓談。タキシードやドレスで着飾っているので、パーティでもしているのだろうか。であればショーは座興なのだろう。
もう1枚のパースは外観を俯瞰したもので、エントランス棟の横に新しく建物ができている。「メディカルツーリズム」だそうで、アンチエイジングサービスが提供されるのだとか。
事業コンセプト・名称や基本方針を読んでも要領を得ないが、富裕層向けの会員制サービスでも始めるつもりなのだろうか。であれば場所を間違えていないだろうか。
施設を6,100万円で買い取り、別に土地の使用料として毎月198万円を支払っていくそうだが、果たしてうまくいくだろうか。向かいの島にIRができ、盛況になれば波及するのだろうか。